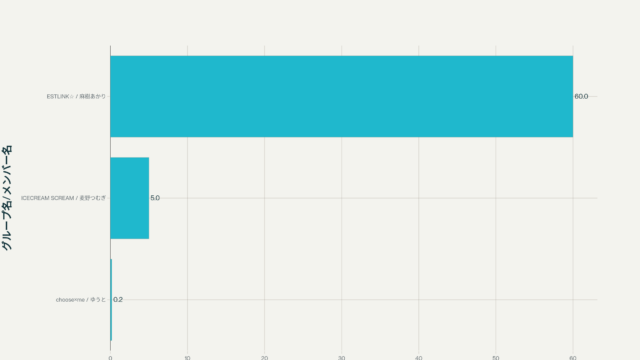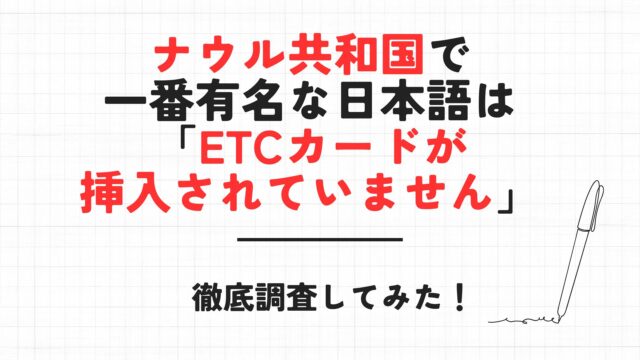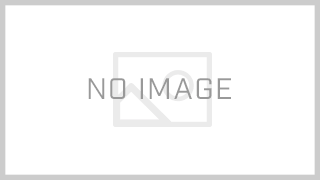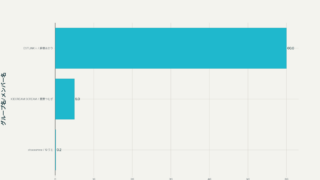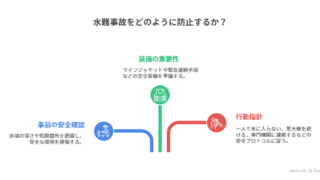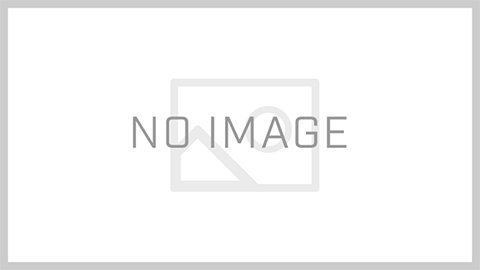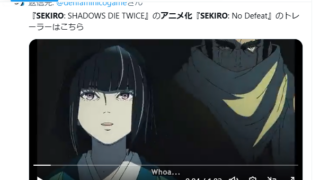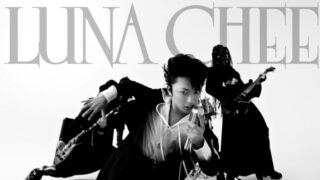はじめに
2024年11月、北海道猟友会が「熊出没に対する発砲拒否を認める」という異例の通知を出したことが話題となっています。
追加で、2025年8月20日、新しい「緊急銃猟制度」の開始を前に、猟友会は全71支部に対して「状況に応じて発砲を断って良い」との追加通知を出しました。
住民を守るはずのハンターがなぜ発砲を拒否するのか?その背景には複雑な法的問題と責任の所在をめぐる課題があります。この記事では、この問題をわかりやすく解説します。
事の発端:砂川市事件とは何だったのか
この問題の始まりは2018年8月に北海道砂川市で起きた「砂川市事件」にさかのぼります。
事件の経緯
北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん(75歳)は、砂川市の要請を受けてヒグマ駆除に出動しました。
現場には市職員、警察官も立ち会い、安全を確認して発砲。子グマを駆除しました。
突然の告発
しかし、現場にいたもう一人のハンターA氏が後になって「池上さんの弾が跳弾して自分の銃床に当たった」と主張し、「金を払わなければ警察に行く」と脅迫。
池上さんが相手にしないでいると、A氏は本当に警察に通報しました。
個人的感想:この告発の動機が理解しがたい部分があります。住民を守る正当な駆除活動に対して、なぜこのような行動に出たのでしょうか。
法的処分の流れ
公安委員会による処分(2019年4月)
北海道公安委員会は「民家に向けて違法な発砲を行った」として池上さんの猟銃所持許可を取り消しました。
ただし、検察庁は起訴猶予処分とし、北海道環境生活部は狩猟免許の取り消しは行いませんでした。
一審判決(2021年)
札幌地方裁判所は池上さんの主張を全面的に認め、
「形式的に法令違反となる余地があることを理由に猟銃所持の許可を取り消すことは社会通念上、著しく妥当性を欠き、違法だ」
として公安委員会の処分を取り消しました。
二審判決(2024年10月)
しかし札幌高等裁判所は一審判決を覆し、
「弾丸が周辺の建物に到達するおそれがあった」
「周辺にいた3人の生命・身体も危険にさらした」
として池上さんの訴えを棄却しました。
個人的感想:一審と二審で全く正反対の判決が出たことが、この問題の複雑さを物語っています。現場にいた警察官は発砲を制止しなかったにも関わらず、後から違法とされるのは理不尽に感じます。
猟友会の苦渋の決断
2024年11月の方針決定
札幌高裁判決を受けて、北海道猟友会は各支部に対して
「自治体からのクマ駆除要請を拒否することも認める」
方針を通知しました。ただし、一律拒否ではなく、現場の支部が判断することとしました。
2025年8月の追加通知
さらに2025年8月20日、新しい「緊急銃猟制度」の開始を前に、猟友会は全71支部に対して「状況に応じて発砲を断って良い」との追加通知を出しました。
個人的感想:猟友会としても住民を守りたいという気持ちと、メンバーの安全を守りたいという気持ちの板挟みで苦しい決断だったと思います。
緊急銃猟制度とは
制度の概要
2025年9月1日から開始される「緊急銃猟制度」は、これまで警察の判断が必要だった市街地での発砲を、市町村の判断で可能にする制度です。
発砲の条件
以下の4つの条件をすべて満たす場合に発砲可能:
1. 住居、道路など人の生活圏に侵入していること
2. 人への危害を防止する措置が緊急に必要であること
3. 迅速に捕獲できる手段がほかにないこと
4. 住民の安全が確保できていること
責任問題の懸念
しかし、この制度では誤射などによる人身事故が発生した際の補償制度が明確でなく、ハンター側が法的責任を負う可能性があることが問題視されています。
個人的感想:新制度自体は迅速な対応を可能にする良いアイデアだと思いますが、責任の所在が曖昧なのは大きな問題です。ハンターが安心して職務を遂行できる環境整備が急務です。
クマ被害の深刻化
統計データから見る現状
– 2024年度上半期の全国クマ出没件数:15,741件(過去最多)
– 2023年度北海道ヒグマ捕殺数:1,804頭(過去最多)
– 北海道内クマ通報件数(2024年):2,556件
人身被害の増加
全国のクマ類による人身被害は2023年で219人に達し、死者は6人。2016年度と比べて約3倍に増加しています。
個人的感想:これらの数字を見ると、クマ問題が如何に深刻化しているかがわかります。だからこそ、ハンターの協力が不可欠なのです。
住民と専門家の反応
住民の不安
「猟友会が拒否したら、それはちょっと困りますよね」
「他にどこへ頼んだらいいんですかね」
といった不安の声が上がっています。
専門家の指摘
東京農工大学の梶光一名誉教授は
「警察や行政が表に出てこないで、依頼された側が処罰の対象になる。誰が責任をとるのかあいまいのまま、これまでの慣習で猟友会に依存し甘えてきた」
と問題を指摘しています。
個人的感想:専門家の指摘は的確だと思います。行政がリスクを民間に押し付けて責任逃れをしている構造が根本的な問題です。
今後の課題と解決策
制度の改善が必要な点
1. 発砲時の責任の明確化
2. 事故時の補償制度の整備
3. ハンターの免責規定の設置
4. 専門人材の育成と配置
### 長期的な視点
野生動物管理学専門家は
「公的機関で体系的に対応できるような制度と部署の配置、人材育成が喫緊の課題」
と指摘しています。
個人的感想:民間の善意に頼るだけでなく、公的な責任として野生動物管理に取り組む体制づくりが必要だと思います。
まとめ
北海道猟友会の「発砲拒否OK」という方針は、表面的には住民を見捨てるように見えますが、実際は長年にわたって住民の安全を守ってきたハンターたちが、不当な処罰から身を守るための苦渋の決断でした。
この問題の本質は、責任の所在が曖昧なまま民間に危険な業務を委託してきた行政の体制にあります。真の解決のためには、制度の抜本的な見直しと、ハンターが安心して任務を遂行できる環境づくりが不可欠です。
住民の安全を守りながら、それを支える人々も守る。そんな当たり前のことが実現される日を願ってやみません。
最後に:この問題は他人事ではありません。クマ被害は全国に広がっており、いつ自分の住む地域でも同様の問題が起きるかわかりません。行政に対して適切な制度整備を求めていくことが、私たち市民にもできることだと思います。
出典元
HTB北海道ニュース: https://www.youtube.com/watch?v=85dIDiwywTw
FNNプライムオンライン: https://www.fnn.jp/articles/-/788764
NHK: https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241125/k10014649121000.html
Yahoo!ニュース(ヒグマ対策新制度): https://news.yahoo.co.jp/articles/33034fc00f5afe5e66dd7a1ecb77c6c4c13cb1b3
Yahoo!ニュース(発砲拒否OK): https://news.yahoo.co.jp/pickup/6549697
毎日新聞: https://mainichi.jp/articles/20250820/k00/00m/040/183000c
共同通信: https://news.yahoo.co.jp/articles/78bf25296c83d434e5f5aef2c67c5e3b58ee79e0
産経新聞: https://news.yahoo.co.jp/articles/672c77db81d41321ecef280eb66365671ba6a160